うらをみせ おもてを見せて ちるもみじ (良寛)
10月に入り、朝夕に涼しさを感じる季節となりました。皆様には慈光のもと、御健勝にて仏恩報謝の日々をお過ごしのこととお慶び申し上げます。冒頭の句は良寛和尚の句です。先日、親戚寺院の十三回忌法要に参勤しました折に、そのお寺の御住職の御挨拶でこの句が紹介され、心に残りましたので今回の御挨拶に紹介いたします。
皆さんの地域の紅葉はどうですか。即得寺の庭の木々はまだ青々としており、紅葉までには、あと一ヶ月以上先のことと思えます。庭に出て、写真を撮りましたが、鮮やかな緑の葉を広げており、若々しさを感じます。
「うらをみせ おもてを見せて ちるもみじ」
この句は良寛和尚の「辞世の句」であるそうです。70歳を超えた良寛和尚は、老いの身の中で「死」を実感されたのだと思います。生涯にわたって寺を持たず、貧しいながらも清らかな生き方を通されました。そうした中で、多くの詩や歌を詠み、また、子供達と遊んだ時等の逸話から慈愛に満ちたお人柄が伝えられています。良寛の命が終焉に近づいた頃、良寛自身が詠んだ俳句であります。「うらをみせおもてを見せ」るとは、自分の本当は人に見せたくない部分も全て自分なのだということではないでしょうか。私は、自分の嫌な面や隠したい面を外に出すことはできません。しかし良寛和尚は、自分の裏も表も全てさらし出さなければ自らの人生を全うできないと示されているようです。あるがままに老い、あるがままに生きるということを教えられます。
親鸞聖人は「外に賢善精進の相を現ずることを得ざれ、内に虚仮を懐けばなり。」と教えてくださっています。


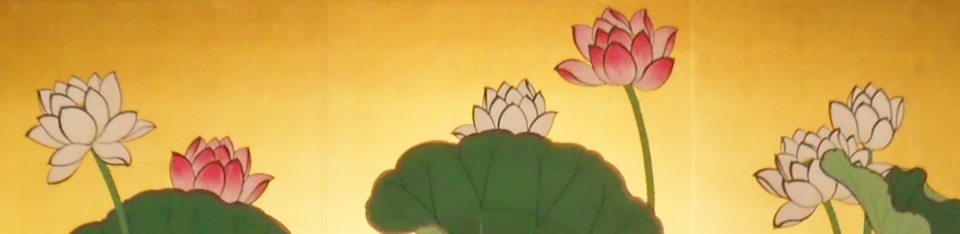












![clip_image002[1] clip_image002[1]](https://sokutokuji.or.jp/wp1/wp-content/uploads/2016/08/clip_image0021_thumb.jpg)







