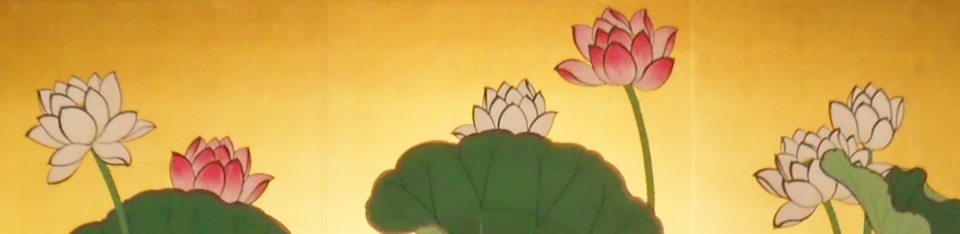難問に出会う
ご門徒の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。一月に入って、北陸や近畿北部を中心に大雪となっております。本堂の軒下には屋根雪が積もり、1mぐらいの高さになっています。
さて、冬は大学共通テストをはじめとした様々な入試が実施されます。受験生の皆さんはこの日を目指して、日々努力を重ねてこられたことでしょう。入試では「難問」といわれる歯ごたえのある問題が出されることがあります。あらゆる知識を総動員し、解法を導き出し、答えが出せた時の喜びは本当に大きなものだと思います。「難問」が潜んでいるのは何も試験問題の中だけではなく、日常生活の中にもたくさんあると感じます。人間関係の難しさや、家計をやりくりする難しさなど、生活の中での「難問」を抱えておられるのではないでしょうか。
親鸞聖人は「浄土和讃」に次のように示されているます。
善知識にあうことも おしうることもまたかたし
よくきくこともかたければ 信ずることもなおかたし
この和讃で親鸞聖人は、私たちが善知識(よきひと)に出遇うこと、教えること、真実を聞くことはとても難しいと示されています。ここで「難しさ」とは、入試問題のような「難問」という意味ではなく、どれだけ努力(自力)を重ねても、達成することができないのが我が身における難しさなのでしょう。私たちは、生活の中で「難問」に出遇うと、何とかしてそれを解決しようとします。その時、私たちには解決の方法がたくさんありますが、私たちはどこまでも「私にとってよい解決とは何か」を考えてしまうのです。「自分という立場」から、物事を見る、聞く、信ずる、ことを繰り返しているのが実は私なのです。親鸞聖人は自分を立場としている以上、物事の解決は「かたし」(不可能である)であると示されたのです。
生活の中での「難問」は、実は私自身に課題があることが多いと感じています。しかし常に自己を立場として考えるため、愚痴をこぼしたり、相手に対して腹を立てるということを繰り返しているのです。
相田みつをさんが「車」という詩を書いておられます。
アノネ どんな車よりもね 構造が複雑で 運転がむずかしい 車はね
じぶんという名の この車なんだな そして 一生の運転手は じぶん
常に自分の思うようにしたい、思うようになるはずだという我が身が、阿弥陀様のはたらきにより照らされたとき、運転の仕方が変わるのでしょう。