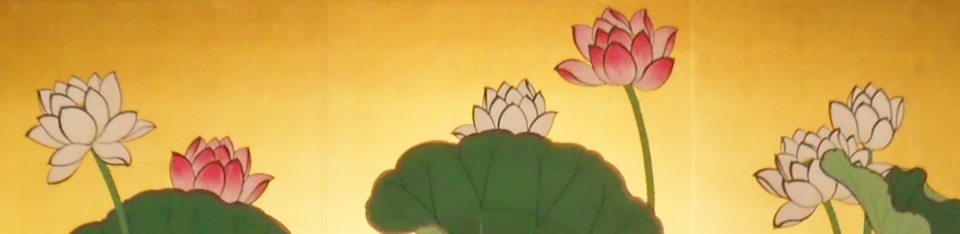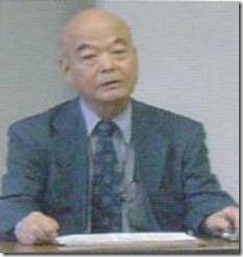6月に入り天候が安定せず、日中かなり暑い日があったと思うと、朝夕は肌寒さを感じる日さえあります。天気予報を聞いていると、各地で梅雨入りとなっています。
即得寺では、6月4日に前住職の13回忌法要を勤めさせて頂きました。平成16年6月16日がお命日で、忘れることのできない日であります。あれから12年が経過したとは思えないぐらい、つい最近のことと感じるのです。そして、住職の還浄は同時に私にとって住職就任ということと、どのようにお寺や門徒の方と向き合うかということのスタートでもあったのです。その意味でも今回の法事は、格別の思いをもってお勤めさせていただきました。12年前(平成16年)、私は高島高校の教頭として勤務しており、毎日が追われるような日々を送っておりました。会議や出張、書類の作成など校務に専念していたわけですが、それは父(前住職)がいてくれたお陰であったのです。父が亡くなると、すぐに本山での住職修習研修を当時の総代長の霜降さんと共に受講し、本山より正式に住職を任命されました。その後、平成25年3月に教職を定年退職するまでの日々を振り返り、「自分自身よくやってこられたなぁ」と感じると同時に、「その時々の総代の皆様、ご門徒の皆様のご理解と家族の協力がなければ今日の日を迎えることはできなかったなぁ」と感じています。
私にとっては前住職が目標であり、前住職のように法話やお勤めができるようになりたいと考え歩んできました。12年が経過し、今回の13回忌法要にはようやく自分自身を振り返る機会をいただいたと感じています。前住職にはまだまだ及びませんが、少しずつ住職ということがわかり始めたと感じています。
昨年の「高島秋講」の時にも感じたのですが、「この法要を前住職と一緒に迎えられたら、どんなに喜んでくれただろうか」と考えてしまいます。「高島秋講」をはじめとする聞法のご縁を心から喜ぶ人であったからです。しかし前住職が健在であれば、きっと私は父にすべてを任せてしまい、現在のようにお寺には関わっていなかったのではないかと思えます。その意味では父は、浄土に還ることにより私の役割を作ってくれたということに頷くばかりです。
法事ということは、亡き方に出遇う場であります。亡き方がどんな生き方をされたのかを訪ねることが大切です。同時に亡き方から私自身が問われる場でもあります。自分自身をしっかりと生きているかどうかが問われるのです。時は確実に経過し、その時間だけ変化します。しかし変化しないものもあります。それは、亡き人への思いと、亡き人からの願いです。即得寺では前住職の7回忌の時から時間が経過し、その間に若夫婦が誕生し、その夫婦に長女が誕生するという出遇いをいただきました。13回忌が終点ではなく、17回忌への出発点となるような歩みを始めたく考えます。