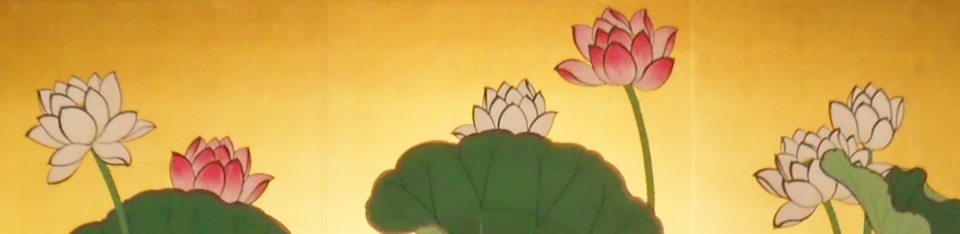ありのままの「いのち」
先日、一冊の本を手にする機会がありました。「お誕生日おめでとう、生まれてくれてありがとう」という題の本(真城義麿著)です。その中で、『私が人間に、そして「私」に生まれた意味はどこにあるのでしょうか。』という問いが投げかけられていました。私たちは、人間に生まれたことには違いありませんが、さらに重要なことは「自分」に生まれたということにあると思います。
今から二千五百年前にインドの北部(現在のインドとネパールの国境付近)で、釈迦という人が生まれ、仏教を説かれました。釈迦に関する説話は数多く残っておりますが、特に誕生に関して印象に残る説話があります。釈迦は誕生の際、七歩あるいた後に、「天上天下唯我独尊」と声を発したと伝えられています。誕生直後の赤ちゃんが、歩き、言葉を発することは現実ではあり得ないことでしょう。しかし、この説話が私たちに伝えている意味は何であるかを考えるべきです。 「天上」とは、自分を取り巻く状況が、比較的自分に都合良く、思い通りに進んでいる状況のことを指します。逆に「天下」とは、なぜ自分だけがこんな辛い目に遭うのだろうかと思ってしまう、つまり思い通りに進まない状態を言います。「天上・天下」とは「どんな状況であっても、どんな境遇になっても」ということを指しています。
「唯我」とは、存在しているどの一人も、かけがえのない人であることを表しています。誰とも代わることのできない存在なのです。私たち一人ひとりが、他の人と代わることのできない、代わりがきかない人間なのです。
「独尊」の「独」は、何も加えなくとも「それ自身で」という意味です。成績や所得や地位が高いかどうかではなく、その人がその人として生きていることが尊いということです。身につけた技能や能力が尊いというのではありません。
私たちは、自分のありのままの「いのち」の尊さに改めて目覚めるとともに、支え合い、尊び合う、互いの「いのち」に「ありがとう」と感謝し合いたいものです。