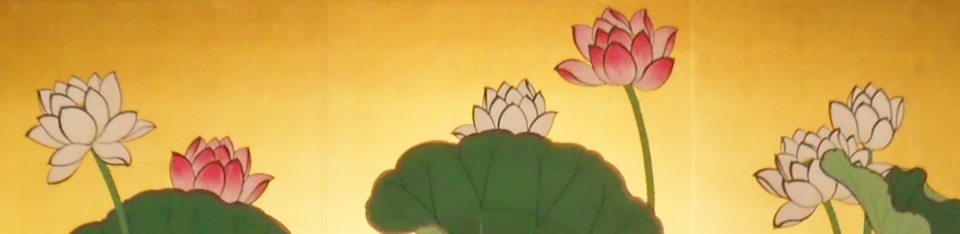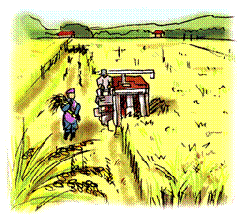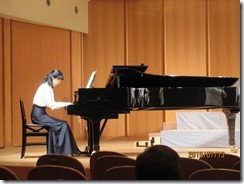「いのち」に出遇う
感染症の拡大に思う
昨年末に中国の武漢で発生した新型肺炎(コロナウイルス)は中国国内だけに留まらず、今や全世界を巻き込んで猛威を振るっている。中国では七万八千人を超え、死者は二千七百人余りに達している。日本でも百五〇人余りの感染が確認されています。(2月26日現在)日を追うごとニュースで伝えられる内容が変化し、深刻な状況が感じ取れます。
当初は報道が示すとおり、直接中国への渡航されたこと、または中国からの旅行者を受け入れることにより感染されたのだと考えていました。しかし現時点では海外渡航歴の有無にかかわらず感染者が報告され、感染の拡大が予想されます。 今回の感染の最大の難点は、治療薬がないということでしょう。人類の歴史はまさに、病気との闘いであったといえるのではないでしょうか。数々の伝染病の原因を突き止め、薬を開発し、治療法を確立してきた歴史があります。「健康」「命」をそうやって願ってきたと言えます。今回の新型ウイルスに対する治療薬も、一刻も早く開発されることを念じずにはいられません。
医療関係者のご苦労を思う
今回、国内感染で思うことは、治療に当たっておられる医師や病院関係者、政府や自治体の関係者に敬意を表したいということです。直接治療や業務を担当されておられるご苦労を感じずにはおれません。自らが感染するリスクを負いながら、一生懸命に働いて下さっているお姿を思うと、ただ頭が下がります。今回のことで、どれだけご家族も心配されておられるかと思うと、胸の痛みを感じます。一日も早く、新型肺炎の感染が止まることを願っております。
「いのち」に出遇う
私たちが病気になれば、病院のベッドで身を委ねなくてはなりません。しかし、病気の身体を引き受けることができないのが我が心です。現実を受け入れることができず、病気に対する不安を感じ、健康は善、病気は悪だと思い込むのです。
ところが、病気のときも健康なときも、共通の事実があります。それは「いのち」が与えられているということです。「いのち」が与えられていなければ、病気にもなれないということです。健康なときも病気で苦しいときも、生きているという事実が前提になっています。病気であろうが無かろうが、老年であろうが若かろうが、私にとって共通の事実は、「いのち」が与えられて生きているということなのです。その「いのち」をどういただくかということがとても大切な問題であります。
毎月、お茶所で「歎異抄の会」を開いていますが、二月の会で、ある方が「ご院さん、私は一度自分の心臓を取り出して、お礼が言いたいですわ」と仰いました。考えてみれば、口から愚痴や不満をこぼしながらの日々ですが、心臓も腎臓も文句ひとつ言わず働き続けているのです。私が眠りこけている時も、働き続けているのです。そうした「いのち」に向き合うとき、手を合わさずにはおれないのです。そして、「自分に力で生きているのではなかった」と気付かされたとき、「生死の苦海」が「功徳の大宝海」に転じて下さるのだと思います。